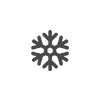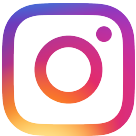HIDABITO 022
渋草焼 窯元 芳国舎 松山 正和 氏
原料を吟味するからこそ丈夫な磁器になる
目の前の素材に向き合うことが大事なんです
土壁づくりの陶房に入ると、壁いっぱい無造作に並んだ無数の器に出迎えられた。一つひとつの骨董然とした面構えを眺めながら、窯元の歴史に思いを馳せる。陶房の中はひんやりとして昼間でも薄暗い。ガラス窓から差し込む光のやわらかな陰影が、写実的な油彩画のように崇高な空気感を醸し出す。
「手前が絵付け、半分から奥がろくろ場です。絵付け師は絵を描く。ろくろ職人は形成して釉薬で仕上げて窯も焼くっていう、そういう仕事をしています」案内してくれたのは代表の松山正和さん。ろくろからこの仕事に入り、今は仕上げの釉薬と窯が専門だ。絵付けは長男の功次郎さんが、次男の宗央(ときお)さんがろくろを任されている。

「家内がね、ここの娘だったんです。三姉妹の次女。私は農家の長男でしたから当然嫁にもらう気でおりましたが、家内の姉が先に嫁いでしまった。それで婿養子に入ってもいいってポロッと言っちゃったんです。田舎なんで、うちの親戚中が集まって親族会議になりました。その中で弟が『田畑は僕が継ぐ』と言ってくれてね。あのひと言がなければ、私は今ここにいなかったかもしれない」
窯元の娘との結婚を機に、松山さんは縁もゆかりもなかった作陶の道に入った。相当、覚悟の要る決断だったのではないか。話しやすい気安さに乗じて、奥さんへの愛の力が為せるわざですねと言うと、「それしかないね」と、直球な答えが返ってきた。飾らない率直な人柄が気持ちいい。
「結婚して多治見市にある岐阜県陶磁器試験場に、2年半行きました。県の職員の助手として働きながら絵付けやろくろの技能研修を受けるんですが、カリキュラムが組まれているわけではなくてね。自発的に学んでいくしかない中、最初のうちは図書室で借りた焼き物の専門書を一日中、読み漁りました。この頃に詰め込んだ知識や、生地と釉薬を研究する科で覚えた基礎が、自分のベースになっています」

磁器と陶器の違いさえも知らなかった青年が、飛び込んだ渋草焼の世界。その歴史は古く、江戸末期の天保12年(1841年)まで遡る。高山が江戸幕府の直轄地だった当時、高山陣屋の郡代が九州肥前や加賀九谷より職人を招いて陶磁器製造所を渋草という地名の場所に開窯したのが始まりだ。のちに尾張瀬戸よりも職人を招いている。明治12年(1879年)になり、勝海舟が「芳国社(舎)」と命名。そのときこの陶房が建てられ、職人たちが代々、伝統技術を受け継いでいる。
「高山に戻ってから、ろくろデビューしました。25歳でやっと自分の手を動かしました。義理の父は絵付け師だったので、私は腕の良いろくろ職人の師匠について。ろくろから窯の焼入れや釉薬まで、形成に関わるすべてを修業しました」
一意専心で打ち込みながら、松山さんは陶房で長年使われてきた石膏型の改良にのめり込んでいく。「八角形の皿や急須など、複雑な形の器は石膏型に泥状の粘土を流し込んで作るんです。その型が雑な造りやったんです。今の時代は雑さは味わいにもなるけど、私は几帳面な性格なので、たとえば八角皿なら重ねてもズレないくらい精巧に作りたかった。それで、10年ほどかけて全部作り直したんです」
この頃、芳国舎には、絵付けもろくろも熟練した技術を持つベテラン職人がたくさんいた。「ろくろをやるより、石膏型の改良の方が私のやるべきことやと思ってね。陶磁器試験場で覚えた知識がここへ来て役立ちましたね」

石膏型でようやく自信をつけた頃、義父が69歳で他界。松山さんが急きょ陶房を受け継ぎ、気がつけば20年以上の歳月が経つ。「私はここを継ぐために他所から迎えられました。よそもんだから、自分の代で潰してはいかん、次に受け継ぐまでは死んでも渋草焼は守り抜かなかんと、その使命感でこれまでやってきたような気がします。息子二人、入ってくれたけど、肩の荷はまだまだおりませんね」そう言って、松山さんはいたずらな表情で微笑んだ。
せっかくなので、息子さん二人に「伝統を受け継ぐこと」への思いを聞いてみる。「作り手と使ってくれるお客さんとのやり取りが、うちの歴史になっていると思うんです。だから僕は、お客さんのために全力を尽くすだけです」やわらかな口調で話す長男の功次郎さんに、一切の気負いはない。幼いときから継ぐことを前提に育ち、反発心で一度は違う道へ進んだが、看板絵付け師として渋草焼特有の青の魅力をさまざまな器で伝えている。
「僕はそこまで重くは捉えてなくて。やっていかなかんかな、ぐらいです。ひとまず僕は僕のできることをやるって感じです」ろくろと向き合う真剣な表情とは打って代わり、笑顔が絶えない宗央さん。師匠でもある父から「もう俺をこえとる」と、形成の技術はお墨付きだ。
父子それぞれが技量を発揮し、一つの磁器ができ上がっていく。こうして伝統工芸は確実に受け継がれる。静寂な陶房の片隅で、渋草の神様が見守っているような気がした。

渋草焼 窯元 芳国舎
10:00〜17:30
不定休
| 社名 | 株式会社芳国舎渋草製陶所 |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県高山市上二之町63 |
| 電話 | 0577-34-0504 |